Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第1回建築レビュー
いよいよ始動
新年度の山中研究室が始動した。
今年からは新たに落合研究員を迎え、4年生、大学院生、研究生や聴講生を併せ、過去最高となる総勢20名が研究室会議に顔を揃えた。
新たな試み:「建築レビュー」
第1回目はM2酒井が西沢大良氏の近作として「沖縄KOKUEIKAN商業ビル(2006)」と「駿府教会(2008)」を取り上げ発表を行った。今年度から山中研究室での新たな試みとして、ここ数年に発表された近作を題材に建築の分析・考察を行う「建築レビュー」が行われる。
厚みをもった境界
沖縄KOKUEIKAN、駿府協会(ほかの作品においても見受けられるが・・)ともに特筆すべき特徴は壁や屋根スラブが非常に厚いことだ。( 駿府では壁厚760ミリ、沖縄KOKUEIKANにおいては1,100ミリ)。そしてその「壁」の内部は中空、あるいは幾層にも木材が積層されている。このことから西沢にとっての壁や屋根とは、単に内部と外部を定義付ける非空間的な「パーティション」としてではなく、双方の間に挿入された”境界スペース”であることがわかる。
デザイン対象の変化
このことを敷衍させると、利用者のアクティビティによって切り分けられている現行の「ビルディングタイプ」は、 建物の平面や立面などではなく、空間を覆う各エレメントの各活動様式へのアダプテーションによって成立するのではないだろうか。(これは従来の建築デザインにおいての操作対象とされてきた「輪郭のデザイン」とは異なる志向である。)西沢は建物の外形や平面には特別なことをしない。彼がデザインする要素は建物の「壁」や「床」あるいは「屋根」という建築の構成要素そのものだ。各エレメントの厚みを増減し、重層する部材の構成を組み替えることで採光や室温、湿度をはじめとする内部空間の”状態”を操作している。
アンチ・ユニバーサルデザイン
”この厚みをどのように解釈すれば良いのか‥?”
議論の焦点はそこへ収束していく。
いわゆる「ダブルスキン」とこの”厚み”との差異はなんなのか。
これに対し山中が、”アンチ・ユニバーサルスペース”なのではないか、との見解を示す。今回取り上げた2作ともに、各空間の平面はまさにユニバーサル・スペースそのものだ。しかしそれを纏う各要素の”性質”を操作することで、文字通り”どこへでも適応可能な(=Universal)空間”としているのではないか。(これはまさに”本家”ユニバーサルスペースがイデオロギーとして掲げ、そしてなし得なかったことだ
近代のガラス・コンクリートに対して木を用いていること、そして立ち現れる空間はユニバーサルスペースとは大きくかけ離れた様相であることからも、これらの作品はユニバーサルスペースへのアイロニカルな批判なのではないだろうか。
新年度初の研究室会議にも関わらず、4年生も含め各メンバーからの活発な意見が場をもり立てた。議論することで様々な知識や感性、アイデアが引きだされ、より豊かなものを生み出す土壌が研究室に生まれるはずである。次回は研究室プロジェクトも発表される予定だ。
酒井
【参照資料出典元】
1. 新建築2008年11月号/新建築社
2. Taira Nishizawa WOODEN WORKS 2004-2010/INAX出版

沖縄KOKUEIKAN 模型/断面図
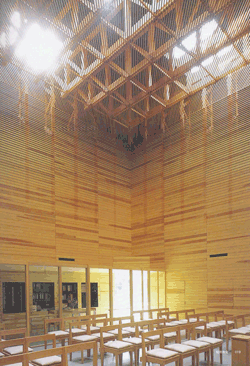

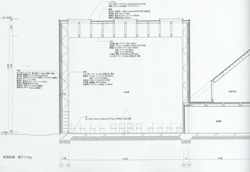

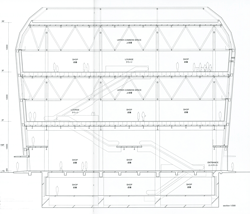
駿府教会 外観/内観/断面図
◁ back next ▷
