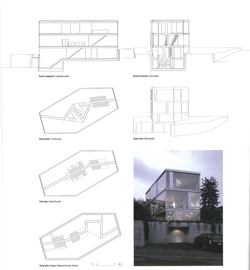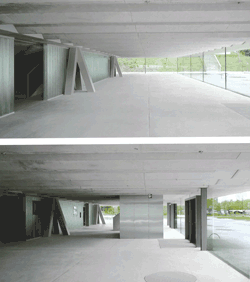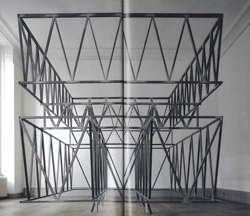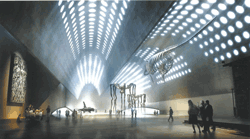Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第2回建築レビュー
プロジェクト、続々
二回目となった今回の研究室会議では冒頭にM1、M2、研究生から、昨年取り組んだ(あるいは現在も進行中の)プロジェクトの報告、2回目となる建築レビュー、そして修士研究発表1題、卒業研究発表2題が行われた。
ー 建築レビュー#2「クリスチャン・ケレツの建築」/発表者:矢嶋宏紀(M1)ー
第二回目となる建築レビューをM1矢嶋が担当した。
スイスの建築家クリスチャン・ケレツの建築5作品をとりあげ、彼の作る魅力的な空間を巡ってエキサイティングな議論が繰り広げられた。
彼のつくりだす空間は柱、梁、ブレースといった至極単純なエレメントによって成立している。「一枚壁の家」、「ロイチェンバッハの学校」、「フォスター通りのアパートメント」いずれの積層建築も平面形は変化しない、というよりも変化させないことで空間に強い”枠組み”とでもいうべきものをつくりだしている。その強いフレーミングに対し、各内部プランや階高を微妙に変化させることで空間に”揺らぎ”とでもいうべき不安定さが生まれているように思えた。(ワルシャワ現代美術館においては曲率は異なれど同一種のヴォールトを並列に反復させることで同様の空間体験を生み出しているといえる。)このことについて山中は、「”つよい秩序を与えるもの”と”乱雑さを生みだすもの”が同時に存在している」との見解を示している。
建築にあてがわれるボキャブラリーを限りなく少なくすることでより建築本体の存在感が消し去られ、結果として各フロアプランや階高の差異、あるいは各エレメント配置の変化という”乱雑さ”がより如実に浮かび上がるのだろう。
「不安定な状態にあるバランス」
この言葉は矢嶋が発表に用いた伊東豊雄の文章(a+u2005年6月号掲載)から引用した言葉だ。
現代建築の向かう一つの方向性を示す言葉として用いられたこの言葉は、ケレスの建築を言い表すのにまさにうってつけの言葉ではないだろうか。
”ひとつひとつを断面的に切り取って眺めてみると不安定でありながらも、全体としては安定が保たれることでダイナミックな空間が創造できる”
「動的平衡」という現代建築が持つ一側面が、今回の発表/議論の中から鮮明に浮かび上がった。
「空間を読み解く面白さ」
新年度発足後2回の建築レビューが行われた。 非常に得るものの多い時間となっているように思う。
4年生からも「建築への知識が深まりとても勉強になる」(奥富)との声も挙がっている。
多くの建築を読み解くことで、設計者が創り出す建築空間の背景にあるコンセプトや思想が垣間みえる。
この瞬間がとても面白い。
今後も建築の知識を養う場として、この試みを継続していきたい。
酒井
【参照資料出典元】
1. a+u 2004年6月号/新建築社
2. a+u 2010年8月号/新建築社
3. a+u 2011年1月号/新建築社
-
4. EL CROQUIS 145 CHRISTIAN KEREZ
2000-2009

一枚壁の家 外観/平面図/断面図
ロイチェンバッハの学校 内観/構造モデル
ワルシャワ現代美術館 外観/内観