Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第3回建築レビュー
建築学総合演習のテスト結果発表という、4年生にとっての一大イベント(卒業がかかっている)から始まった三回目の研究室会議。一喜一憂の声が漏れる中、第三回目となる建築レビューと、修士研究発表一題が行われた。
今回は修士研究で住宅遺産の保存活用という史的な研究をされている長島早枝子さんが主体となる会議となった。
―建築レビュー#3「アメリカにおけるモダンハウスの保存事例」/発表者:長島早枝子(M2)―
第三回目となる建築レビューをM2長島が担当した。
ピエール・シャロウの「ガラスの家(1931)」、アルバート・フライの「アルミネア・ハウス(1931)」、バックミンスター・フラーの「ウィチタハウス(1947)」、ピエール・コーニッグの「ケーススタディハウス№22(1959)」の4作品いずれも現代まで保存されてきた建築が取り上げられ、歴史的な建築たちを、保存という観点から紹介した。そこから改めて気付かされる事柄があり、皆の知的欲求を擽る刺激的な発表がなされた。
「レトロフューチャー的な魅力と保存」
今回紹介された4つの建築は工業住宅であり、量産を目的にされた節がある。また当時の人々にとって(あるいは現代の私たちにとっても)、どこか未来志向的で希望を与えてくれるような建築のようにも思える。
ガラスの家はスチールなど工業部材を用い、工業住宅として施工側に対する提案でもあったことから、未来に働きかけている。アルミネア・ハウスとウィチタハウスは住むことを前提としていないことから、また近未来的な外観も含めて、これからの工業住宅のモデルルームとして未来に提案を投げかけている。ケーススタディハウス№22は既成の工業部材を用いた工業住宅であると同時に、まるで空の上からロスを眺めているような写真が有名であるが、この空中浮遊感も未来的な感覚を与えてくれる。
このように量産化を試みた工業住宅を、未来のために提案したが、量産化は実現しなかった。むしろこれらは稀有な存在として扱われ、また工業化住宅としての軽快な部材構成が、解体や移動のしやすさに繋がり、現在の4つの建築の保存のされ方と密接に関わっている。
それぞれ竣工した年代は古いが、どこか現代の視点から見ても魅力的に見えることについて山中は「前衛的な工業住宅だからこそのレトロフューチャー的な魅力がある」と示し、そのレトロフューチャー的な魅力こそが、それぞれを保存するためのモチベーションになっているとの見解を示した。
「発表者独自の視点が刺激を与える」
今回で建築レビューは第三回目をむかえ、今年度から始まった試みではあるが、早くも研究室会議に定着しつつある。
第一回、第二回レビューでは最近話題となっている建築家及び建築作品をとり上げてきたが、今回は長島独自の興味と研究範囲により、建築史的に著名な建築をとりあげ紹介した。4年生からも「構造はどうなっているのか、室名を教えてほしい!(櫻井)」と提示された情報以上の興味をもったり、「ウィチタハウスの需要の多さに驚愕したが、ビジネスとして実現させなかったのはなぜか?フラーの意思を誰も継がなかったのはもったいない(山井)」等、“過去の建築が現在にも残る魅力“をそれぞれが感じ取った回となり、発表者の独自の視点が皆に影響を与えていた。レビューでは発表者が毎回違うため、各々の持つ独自の興味や視点を垣間見ることができ、自分の興味の幅も広げることができる場となっている。次回はどんなレビューとなるのか、早くも待ち遠しい限りである。
矢嶋
【参照資料出典元】
-
1."a+u臨時増刊20世紀のモダン・ハウス理想の実現 Ⅰ"
2000年3月
2."a+u臨時増刊20世紀のモダン・ハウス理想の実現 II"
2000年3月
3.20世紀名住宅選集2007年6月
4.10+1 no.382004年

ガラスの家 外観/内観

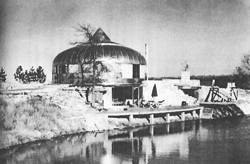
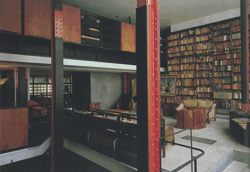
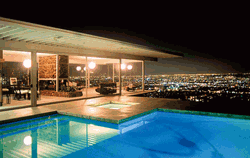
アルミネアハウス 外観
ケーススタディハウスNo.22 外観
ウィチタハウス 竣工時外観

