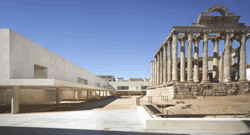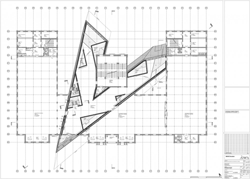Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第4回建築レビュー
5月に入って最初の研究室会議となった。
4月の研究室の始動から1ヶ月経過し、4年生も研究室会議の雰囲気に慣れてきたように思う。今回は建築レビューと卒業研究発表1題、修士研究発表1題が行われた。
―建築レビュー#4「Future Architecture」/発表者:亀井(M1)―
第四回建築レビューはM1亀井が発表した。
2010年以降のリノベーション、コンバージョンの海外事例5つを取り上げた。5つの事例は「歴史的建築物に対してのリノベーション」が2つ、「資源を建築化し、再利用したコンバージョン」が3つに分けられる。
リノベーションの2つは、「Temple of Diana(2011)」主に遺跡観光用の見学施設の事例、「Dresden’s Military History Museum(2011)」ドレスデン軍事史博物館の増築の事例である。
コンバージョンの3つは、「Cutty Sark(2012)」が19世紀の帆船を展示スペースに、「Tubo Hotel(2010)」が土管をホテルに、「Oil Sailo Home(2011)」がオイルタンクを集合住宅に、それぞれ再利用して建築化した事例である。
「建築を読み込む力」
3つのコンバージョンの事例にはどれも資源の再利用など、環境について配慮が見られる。「Oil Sailo Home」のみコンペ案であり実現はしていないが、4年生からの質問が多くよせられた。最近注目されている環境テーマや、建築でない物の建築化にコンセプチュアルな部分があり、4年生の興味を引いたように感じた。
学生からの興味を引いたのはコンバージョンの事例であったが、山中や落合研究員の関心はリノベーションの事例2つにあった。
「Temple of Diana」は市街地化していく都市の中にある遺跡を「囲う」リノベーションであり、既存の遺跡に触らない手法をとっている。遺跡側とまち側で異なるエレベーションを作り出すプランとなっていることが読み取れる事例である。逆に「Dresden’s Military History Museum」は既存の博物館に増築部分を「挿入」する手法で真逆の手法をとっている事例である。特に「Temple of Diana」は開口部や吹き抜け、レベル差などシンプルな手法で様々な空間構成を見せている部分が山中に絶賛されていた。
学生と山中、落合では、やはり建築の読み込み方が違うと感じた。今回に限らず研究室レビューでは、この建築のここが面白い!とぱっと見では気づかない部分も議論され、学生にとって本当に勉強になる場となっていると思う。
卒業研究は今回唯一手をあげた大庭(4年)の発表が、他の学生にも刺激になり、今後の発展性のある良い研究発表となった。
山中のアドバイスから、「私塾=商家や長屋の学校建築へのリノベーション」と捉えた建築の使われ方の研究とするか、「藩校=元から学校建築として建てられた施設」として現在の学校建築への繋がりや応用を研究するのか、という面白そうな切り口が二つ挙った。どちらも修士論文まで書けるようなテーマだけに、今後の報告が楽しみである。
修士研究は山(M2)の医療をテーマにした発表が行われた。
小児ホスピスと小児がんセンターの話を主軸にした発表を聞き終え、難しい問題を抱えている小児医療の現状を研究室全員で学ぶ形になった。落合からは「医療の問題と合わせて、建築の問題を探す必要がある」と形に落とすためのアドバイスがあった。
最後に山中から全体に向けて「卒業設計も修士設計も最終的にどういう絵や表現を示すか、そのイメージを持つことが大切だ」と1年間の研究の心構えとなる言葉があり、5月最初の研究室会議を締めくくった。
長島
【参照資料出典元】
-
1."Archidaily” http://www.archdaily.com/
2."Archilovers” http://www.archilovers.com/

Temple of Diana 外観
Tubo Hotel 外観
Dresden’s Military History Museum
外観/平面図
Cutty Sark 内観