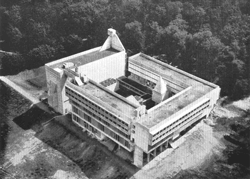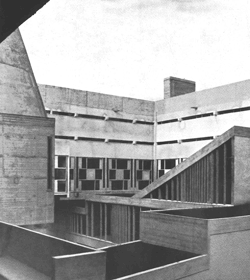Shintaro Yamanaka Laboratory

ボルドーの住宅
外観/内観
ロックフェラー・ゲストハウス
内観
ラ・トゥーレットの修道院
外観/中庭
ニラム邸
内観
review
第12回建築レビュー
今回は第二回ゼミナールとして山中の講義と、修士研究発表二題、卒業研究発表六題の発表が行われた。
-ゼミナール#2「世界を埋め込む」/講義:山中-
建築とは実用的な機能を持たせた制作物ではあるが、同時により多くの意味の媒体でもある。機能という役割だけではなく、象徴的な意味合いがあり、「住居に都市を埋蔵する」という原広司の言葉に象徴されるように、建物とそれに付加する装置が組み合わされて建築が出来上がっていくという事でもある。
ラ・トゥーレット修道院 × ボルドーの住宅
「異質な空間の積層」
コルビジュエによるラ・トゥーレットの修道院はドミニコ教会の修道院、研修所が積層され、世俗との関係を断ち切った場所にある。ル・トロネの修道院の中庭にある瞑想と思索の空間が参照され、修道士にとっての世界の全てがそこに存在する。
コールハースによるボルドーの住宅は足が不自由な富豪のための個人住宅であり、コレクションに象徴される彼の歴史が展示されたエレベーターシャフトによって、機能と空間が異なる三つのボックスが接続される。
建築の中に世界が構築され、建築の中に世界の中心が存在する。それらは建築的に言えば中庭やエレベーターであるが、それらは機能を越えた象徴性が付加されている。世界を内蔵させる手法としての中庭の精神、"自己対峙"、"反射性"という効用は様々な建築でも散見される。
ロックフェラー・ゲストハウス × 住吉の長屋 × 反射性住居
「閉ざされた中庭」
フィリップ・ジョンソンによるロックフェラー・ハウスや安藤忠雄による住吉の長屋はいずれも密集した都市の中に存在し、閉鎖的な住宅である。その一方で周囲に対して完全に閉じた中庭を持ち、それに対して全面ガラス張りの居室が向かい合うという構成をとっている。その中庭はアクティビティの場と言うよりも、二つの居室が向かい合うための"間"を提供し、鏡面的な向かい合いによって反射しあう様な世界を建築の内に作りだしている。
原広司による原邸や粟津邸、ニラム邸は反射性住居という概念を根底に持っている。原の言う「住居に都市を埋蔵する」という思想、その具体的な手法がこれらの一連の作品に示されている。外観は慣習的な住宅の外観を示しているが、内部に内核と呼ばれる軸線を持った純白の空間がある。その内核に面して線対照に諸室の要素が向かい合うことによって内外が反転し、濃密な対になった空間が住宅の中心に出現する。
これらの建築では外壁という境界面を介して世界が反転している。外部に対して拡大していく世界に対して、内部に縮減されていく世界の無限性を示し、外壁という境界面を介して世界が反転する。
「世界を埋め込む」ことを想起させる建築には、ひとの建築に居ながらにして「世界」を感じられるような仕掛けや、その無限性を内包するような仕掛けが平面や断面に為されている。それらは即物的な建築の評価や経験を超えて、豊かな意味や象徴性をもたらすテクネとなっている。
修士研究
修士論文中間発表を終えたばかりの長島は、発表内容と今後の方針の確認が行われた。
一方、横浜の臨海部で修士設計を行なっている山の発表で議論となったのは水際線の意味のもたせ方についてであった。象の鼻コンペを事例として、水際線の形状や使われ方の可能性について意見がかわされた。
卒業研究
卒業論文二題、卒業設計四題の発表が行われた。
卒業論文はそれぞれ基礎調査が終わりに近づき、分析の段階に入りつつある。卒業設計に関しては、それぞれ設計に向かうためのコンセプトや言葉といったものがいくつか示されるようになってきた。
卒業研究を組み立てていくパーツが揃いつつ有り、それらをこれからどのようにして組み上げていくのか、テーマ決定から次の段階へ。
三大学による合同中間発表を目前にし、卒業研究の方針も定まってきたようである。気を緩めず、悔いの残らないよう走りきって欲しい。
朝倉
【参照資料出典元】
-
1.“Le Corbusier Complete Works” / Birkhauser
-
2.“El croquis 131” / El Croquis
-
3.“TADAO ANDO DETAILS 1” / A.D.A.Edita Tokyo
-
4.“GA DOCUMENT 33” / ADA

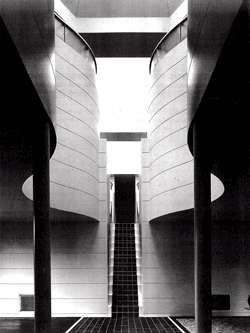
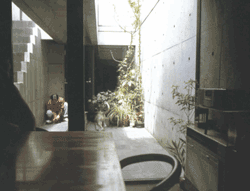
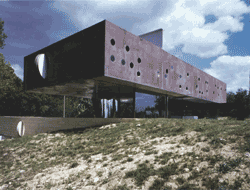
住吉の長屋
内観