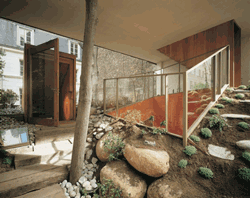Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第7回建築レビュー
5月最後の研究室会議となる今回は、OBの齋藤が顔を出してくれた。こうしてゲストの方が顔を出してくれることは嬉しい。良い緊張感を持って会議に臨むことができる。今後も研究室外に対し、より開かれたものとしていきたい。
−建築レビュー#6「Christian Pottgiesser Architecturespossibles (CPAP)」発表者:朝倉亮(M1)−
第6回目となる建築レビューはM1の朝倉による発表。
パリを拠点に活動する「クリスチャン・ポトギーゼル・アーキテクチュアズポシブルズ」を取り上げ、彼らの設計した作品の中から2003年以降に竣工した3作品を取りあげ、発表を行った。
CPAPは建築家のChristian PottgiesserとアーティストのPascale Thomas Pottgiesserの2人組からなるグループであり、「デジタルな要素と粘土(クレイ)のような素材が同時に存在し、同時に野性的でもある」というユニークなコンセプトを掲げている。
[maisonL]
約5000㎡の広い敷地に建つ住宅である。フラットルーフの四角い棟のヴォリュームがいくつか地面から生えているように見える外観が印象的だ。それぞれのヴォリュームが個々のパーソナルスペースとなっており、地下階の部分が家族の共有スペースとなっている。幾何学的な四角い棟に対して地下階のルーフは柔らかな曲線となっている。
[pons+huot]
古い倉庫をオフィスにリノベーションした作品だ。巨大なテーブルが曲線を描いており、そのテーブルの下に潜ると休憩室や会議室が現れる。テーブルからは木が生えていて、オフィス全体がランドスケープのように感じ取れる。
[galvaniz]
パリの住宅。四角いヴォリュームが隣り合う建物に挟まれて浮いているような外観で、その下を緩やかな丘のようなランドスケープのような曲面の土の床がリビングのヴォリュームに対し対称的な様相を呈している。対称的要素が断面上に混在していることで、住宅の中に見慣れない光景があらわれている。
山中はこれらの作品に対し、「建築家の幾何学的な発想とアーティストの自由で自然的な発想をまず明確に分離し、その二項を再度うまくミックスさせている。それがこれらの新しい風景を生み出しているのではないだろうか。」という興味深いコメントを示している。
建築家だけでなくアーティストと恊働することで、より豊かな空間を生みだしている良い事例だ。
ー研究発表ー
修士研究は長島と酒井が発表した。7月には1回目の修士の中間発表が控える中で、二人とも苦しんでいるように感じた。
卒業研究は田中と長澤が発表を行った。特に田中の発表では、研究対象として挙げた十条地区に関するユニークな見解が示された。
この一帯のもつ独特な空間構成を分析し、まち路地のもつ界隈性を明らかにするというものだ。今後の展開が楽しみなテーマだ。
5月が終わり6月になるこの時期は、研究テーマがそろそろ決まり始める頃だが、去年に比べると全体的にペースが遅いように思う。人前に立って発表することで初めて気付くこともある。批判されることを恐れず、積極的に会議で発表、発言することが会議を実りあるものにするはずだ。
今後は自主ゼミも織り交ぜながら会議を進めていく。より積極的な参加を期待したい。
杉本
【参照資料出典元】
-
1."a+u 499 12:04” /株式会社エー・アンド・ユー
2.”CPAP HP”
http://www.pottgiesser.fr/christian_pottgiesser_architecturespossibles/CPAP.html

pons+huot 外観/内観
galvaniz 外観/内観
maison L 外観/内観