Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第8回建築レビュー
今年度の研究室が始動して2ヶ月余り、例年に比べて4年生の欠席者が目立ち、研究室としてもう一度しっかりと気を引き締め直したい時期である。今回は建築レビューと卒業研究発表は3題、修士研究発表は3題が行われた。
—建築レビュー#8「現代の宗教建築」/発表者:杉本将平(研究生)—
第7回目となる建築レビューを研究生の杉本が担当した。今回は、過去10年以内の宗教建築を対象としており、ジョン・パーソンの「ノヴィー・ドヴール聖マリア修道院(2004)」、ピーター・ズントー「ブラザー・クラウス野外礼拝堂(2007)」、Bunker Arquittectura「La Estancia Chapel(2007)」、ウンドゥラガ・デヴィス・アルキテクトス「聖修の礼拝堂(2009)」、SeARCH「シナゴーグLJG(2010)」の5作品を対象とし、宗教的精神を現代建築にどう反映させて空間を構成しているのかについて紹介された。学生たちにとって普段なじみの薄い宗教建築に触れるいい機会となった。
「ノヴィー・ドヴール聖マリア修道院(2004)」は、荒れ果てた農場という強いコンテクストを持った敷地に建てられており、一部新築の建築である。「ブラザー・クラウス野外礼拝堂(2007)」は、112本の木の幹を円錐状に組み、そこにコンクリートを流し込むことで、内部空間はそのまま木を表し、コンクリートを打ったときのパイプの穴はそのまま残し、光がそこから入るような空間となっている。「La Estancia Chapel(2007)」は、広い公園の中で閉じつつも開放的な空間をつくるために、半透明のガラスの壁の使用をしており、一枚一枚のガラスの間には隙間がある。現代の宗教建築にみられる小スケールの空間となっている。「聖修の礼拝堂(2009)」は、チリの南部に位置しており、十字の軸線に構造壁があり、構造壁が地面から浮いていることにより建物全体を軽く見せている。構造壁の下部の隙間から内部にアプローチができるようになっており、内部空間は、コンクリートに木板を張っており、周囲の明るい空間から内部の暗い空間へと導くことで、宗教的な意味合いを強めている。「シナゴーグLJG(2010)」は、内部の礼拝堂の構造がそのまま外観へ現れており、ユダヤ教独特の皆が同じ方向を無垢空間となっている。今回、5作品の発表が行われたが、それぞれの作品の選ばれた理由などが聞いている側としては分かりづらい面があるように感じた。宗教建築という括りであっても、礼拝堂や結婚式場では意味合いがぜんぜん違うし、それぞれの建築の意図があまり伝わってこなかったかもしれない。次回の発表では、杉本自身の視点をしっかりと持った発表を期待したい。
「研究」
修士研究では、酒井と長島と山の3人の発表がそれぞれ行われた。酒井と長島に比べて研究の方向性があまり定まっていなかった山であったが、山の研究は地元である横浜の臨海地域(横浜インナーハーバー)を対象とした研究になっていきそうである。臨海地域だからこそできる提案の方向性を早く探っていってほしいものである。その中で、先生の「学生の設計は条件が少ないため、自分で制約条件をどうつくるかが重要である。制約条件は最終的なかたちを想像しながらつくっていく。」という言葉がとても印象的であった。
一方で、卒業研究では大庭と桜井と山井の3人の発表が行われた。研究室会議を重ねていく毎に、自分の研究を深めていく者がいる一方で、毎回自分の発表する研究内容が変わってしまう者もいる。研究があまり進んでいない者ほど、今年度から行われている自主ゼミを有効に活用してみたり、先輩や同期に話を聞いてもらうなどの、積極的な動きをみせていく必要があるのではないか。
【参照資料出典元】
-
1.“a+u 08:04” / 株式会社エー・アンド・ユー
-
2.“a+u 11:12” / 株式会社エー・アンド・ユー
-
3.Elcroquis John Powson 1995-2005
-
4.http://www.archdaily.com

ノヴィー・ドヴール聖マリア修道院
内観
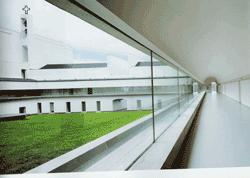

ブラザー・クラウス野外礼拝堂
外観

聖修の礼拝堂
外観/断面構成

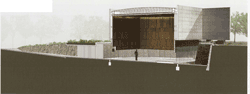

La Estancia Chapel
外観
シナゴーグLJG
内観
