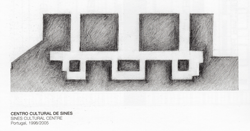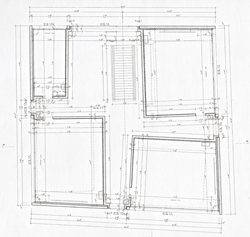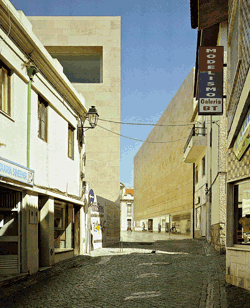Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第9回建築レビュー
前期授業も終わりに近づき、課題の提出や修士研究の中間発表、大学院試験等、それぞれの活動も慌ただしくなってきた。
今回は建築レビューと修士研究発表二題、卒業研究発表五題の発表が行われた。
−建築レビュー#8「内部と外部/表と裏/ヴォリュームとヴォイド/建築と都市」/発表者:酒井(M2)−
大学院生それぞれによる建築レビューが行われ、今回の建築レビューは一周りして再びM2酒井が担当した。
今回はアイレス・マテウスによる建築二作品とヴァレリオ・オルギアティによる建築一作品の三作品の発表となった。それぞれの作品はネガとポジのような二つの要素の対比によって設計が行われている。
まずアイレス・マテウスによる作品のひとつ「SINES CULTUAL CENTER(1998-2005)」はオフィス・ホール・図書館・ギャラリーの複合施設であり、周囲の建物に馴染み、街路が連続したような外観をしている。断面構成に特徴があり、街路のように連続したヴォイドとマスなヴォリュームが浮いたような構成である。「FURNUS MONITORING AND RESARCH CENTER(2008-2010)」は自然観測所と宿泊棟からなる建築である。それぞれ内部の形状は異なるものの、ヴォリュームの引き算によって空間が作られ、残ったマスの部分に水回り等が収められている。
ヴァレリオ・オルギアティによる「SCHOOL IN PASPELS(1996-1998)」は学校建築であり、外壁と内壁の設えや位置が異なり、外観と居室内ではそれぞれ異なる見え方を空間が生まれている。内部と外部とのギャップは、皮をめくられ、都市の裏側を見たような景色として広がっている。
「内と外という二項対立でない解答」
今回紹介された三作品は、外部に対しての内部ではなく、「敷地の上にまず都市が作られ、そこに建築的な表皮が加えられる。だから建築空間の中に都市的空間が現れる。つまり、都市の上に建築が重ねられている。」(10+1 No.35 松田達)という手法によって二項対立だけではない様々な関係性が生まれていた。内部に対しての内部を作ることによって、相対的に外部を作っていくような建築であり、「都市と建築をあらかじめ別のものとする視点はない」のである。
「都市のスケールから外部を決定し、内部を決定する手法は自分たちの設計にも生かせるはず」と山中が述べたように、設計プロセスとして参考にすべき点が多く見られる建築レビューであった。
修士設計は7月末に中間発表を控え、プログラムや敷地の選定も大詰めとなってきた。昨年度と比べて足踏みをしている感もあったが、それぞれ臨海地域での新たな提案として、方針を固めつつある。
対して卒業研究は、研究テーマが決まっている者と、そうでない者との差が開きつつあるように感じる。授業時間から開放される夏休みは研究に打ち込むチャンスである。研究テーマが定まっていない者は今一度、自分が研究したい事柄は何なのか、考えて欲しいところである。
朝倉
【参照資料出典元】
-
1.“10+1 NO.35” P.140-143 / 松田達,2004
-
2.“EL CROQUIS 154” / Aires Mateus,2011
-
3.“EL CROQUIS 156” / Valerio Orgiati,2011
-
4.“a+u 02:04” / 株式会社エー・アンド・ユー
-
5.“a+u 07:04” / 株式会社エー・アンド・ユー
-
6.“a+u 11:05” / 株式会社エー・アンド・ユー

FURNUS MONITORING AND RESARCH CENTER
外観/平面図
SCHOOL IN PASPELS
外観/平面図
SINES CULTUAL CENTER
外観/断面概念図