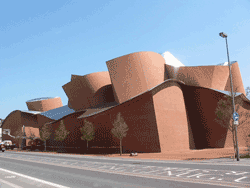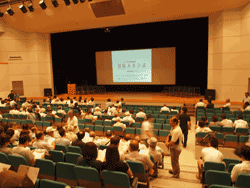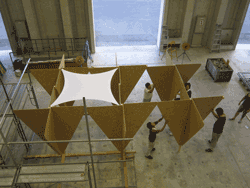Shintaro Yamanaka Laboratory
review
第10回建築レビュー
今回は前半の締めくくりとして前期に取り組んだ研究室プロジェクトが続々と発表された。
#1 雄勝プロジェクト(担当:M1朝倉)
佐藤光彦研究室及び大学院講義「建築デザイン1」佐藤ユニット・東北大学・東京芸術大学・立命館大学と協同
被災した宮城県石巻市雄勝半島の復興計画。佐藤光彦研究室と建築デザイン1佐藤ユニットと協同して進められてきた。
先日被災地にておこなわれた「雄勝未来会議」にて住民にプレゼンテーションを行い、取り組みの成果を1つのまちづくりのベースとなる案として受け取ってもらえたことは大きな成果だ。(http://www.youtube.com/watch?v=1mCyO_hupcE&feature=relmfu)
このプロジェクトは、今後10年近く見届けていくようなものとなるだろう。山中研究室としては下田プロジェクト以来の大がかり且つ長期的なものだ。研究課題としても「地域再生のモデルケース」という日本各地の限界集落にも通ずる非常に大きなテーマ性を含んでおり、今後も学会等へ継続的に発表していきたい。
#2 OSSBプロジェクト(担当:M1矢嶋)
農業廃材麦わらを用いた新素材OSSBによる施設設計のプロジェクトだ。
このプロジェクトは先日行われた日本建築仕上学会主催 建築仕上技術・デザイン競技2012において最優秀賞を受賞した。(http://spacetheory.arch.cst.nihon-u.ac.jp/Yamanaka/2012randr-ossb.html)
11月2〜4日にかけて行われる習志野祭において実物を施工する。施工期間は10月27〜29日、研究室総出での大掛かりな作業となる。先日ものづくり大学にてモックアップ制作が行われたが、建方(たてかた)に際して工夫を要することが判明し、対策の検討がなされた。
素材と結びついたプロジェクトは必然的に構造や施工といった領域も関わってくるため、これも研究室の特徴ある研究テーマとして大切にしていきたい。
—建築レビュー#10「コンバージョン美術館」/発表者:亀井(M1)—
■モーリッツブルク美術館拡張計画(ニエト・ソベヤーノ・アルキテクトス)
■マルタ・ハーフォード美術館(フランク・O・ゲーリー)
今回取り上げられた作品はどちらも既存ストックをベースとしたリノベーションをテーマにしたものだが、山中はどちらの作品にも否定的だった。既存ストックを用いたリノベーションにおいて、建築家が強い手法を振りかざして建物、或いはまちの最終形を与えてしまうことは、その事業に住民をはじめとする第三者が介入する余地をなくしてしまう。
「こうなってしまうと、もう次の手を打つことができなくなる。図らずも建築家の手によって閉じた建築となってしまうのではないだろうか」という山中のコメントは、 先日改修が終わった伊豆下田の住宅改修プロジェクトにも現れているように思う。—※新建築2012年9月号「旧澤村邸改修」(母屋/蔵/公衆トイレと広場)
建物単体のリノベーションに終始せずに、その建築によってまちがどのように変わっていくのか、その射程の長さこそリノベーションの価値なのではないか‥。今回のレビューではそのようなことを考えさせられた。
後期に向けて
8月も終盤にさしかかり、4年生は前期取り組んできた卒業研究の中間発表に向けて追い込みの時期だ。修士研究もこの時期の取り組みは必ず後期に活かされてくる。しっかりと積み重ねていきたい。
9月からは名古屋大学での学会発表に始まり一大イベントのゼミ合宿と慌ただしくなっていく。新たなプロジェクトも複数加わり、研究室は早くもフル稼働になりそうだ。研究室という一つの組織を大切に、取り組んでいきたい。
酒井
【参照資料出典元】
-
1.“a+u 06:04” / 株式会社エー・アンド・ユー
-
2.“a+u 09:07” / 株式会社エー・アンド・ユー

OSSBプロジェクト
モックアップ
モーリッツブルク美術館
外観/断面図
雄勝未来会議
プレゼンテーション
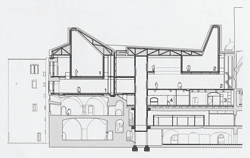
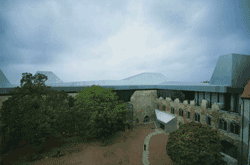
マルタ・ハーフォード美術館
外観/断面図