Shintaro Yamanaka Laboratory
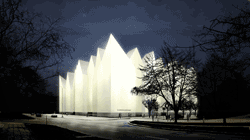
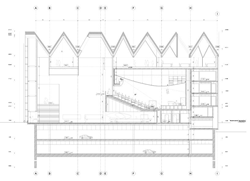
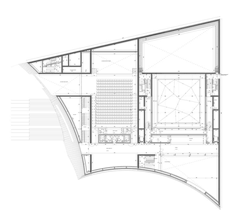
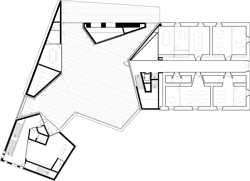


review
第9回建築レビュー
9回目を以て院生による建築レビューは2周目に突入した。また、第1回ゼミナールも読書会という形で行われ、『現代建築に関する16章』(五十嵐太郎)の第一部について討論がなされた。そこで得た知識を基に3年生も建築レビューの聴講生となり、院生の発表が特に期待される回となった。
ー建築レビュー#9「Estudio Barozzi Veiga Architect
s」/発表者:櫻井(M1)ー
スペインのバルセロナに事務所をかまえるEstudio BarozziとAlberto Veigaの建築家ユニットである。彼らが設計した3作品についてレビューが行われた。
■Headquarters Ribera del Duero Wine(2009)
スペインのロアに位置し、街の出入口と呼べる場所に建つワイン工場の会社である。敷地が傾斜となっているため、ホールや研修室といった主要な機能は地階にあり、地上レベルでは展望室や既存の工場施設とつながり、展望室は街の灯台としての明りをもたらす。
■Auditorium Infanta Dona Elena de Aguilas(2011)
スペインのアギラスに位置する劇場である。アギラスは地中海に面し、その他3面を山に囲まれている。敷地は地中海に面する海岸線の一画にある。従ってその形態は海岸線に沿い、母なる海を受容するような流線型となっている。地上レベルにある大ホールと3Fレベルにある小ホールへのアクセスを可能にするロビーは海に面し、窓からはラッセンが好んで描きそうな地中海の風景を望むことが出来る。
■Szczecin Phiharmonic Hall(2007)
ポーランドのシュチェチンに位置する劇場である。シュチェチンはポーランド北西部のドイツとの国境付近にあるため、ポーランド領とドイツ領を行き来する過去を持つ。戦後復元された街並みに溶け込むようにフライタワーの形状や全体のボリュームは尖塔上の形態を並べることで調整されている。
「2種類の線」
これらの作品に共通するものとして、2種類の線が挙げられる。スペインのワイン会社の場合は斜線で構成された外壁から直角に内壁を伸ばしていくことで多様な空間を創り出している。また、地中海に面する劇場では曲線で囲まれた内部を垂直線で割っていく手法をとっている。ポーランドの劇場とワイン会社では既存の街並みに対して、新しい線として挿入している。これら2種類の線によって内部に豊かな表情を創り出すことが出来る。
「Duck的なもの」
読書会の中でロバート・ベンチューリらが『ラスベガス』(鹿島出版会)の中で述べた「あひる」と「装飾された小屋」という二つのモデルについて、「あひる」とはその建物に要求される機能をそのまま形にしたものであり、モダニズムへの批判であるとのことを学んだ。劇場はその性質上「あひる」になることが多く、その都市のアイコンとなる。しかし、Estudio BarozziとAlberto Veigaらは上記の作品においてフライタワーの納まりに見られるように、「あひる」を都市という「池」に浮かべる試みがみられた。これらの手法は今後、卒業設計、修士設計を迎えるにあたって有効な設計手法である。
ーゼミナールー
第1回ゼミナールは『現代建築に関する16章』(五十嵐太郎)の第一部。形態と機能・バロック・斜線とスロープの概念や設計手法について議論がなされた。予定の90分間を超過しての議論となった。1回目とあって、発言がまばらであったが今後、より活発な議論が行われることを期待したい。
ー卒業研究・設計ー
中間発表をへて、卒業研究を引き続き行う学生と研究成果を活かして卒業設計に取り組む学生の両者に分かれた。各研究が多岐にわたり、さらにそれらが深化するに従って発表者は伝える発表が重要になるとともに聞き手も研究の理解が大変になってきた。手を止めることなく走りきることに期待する。
ー修士研究ー
同じく中間発表を経て、その反省と今後の展望が示された。オリンピックの選手村の設計はザハ案の新国立競技場の問題と相まってホットな話題である。代替案ではなく、確実に現状案よりも優れたものでない限り評価されないというプレッシャーも掛かる。その他、温泉街の活性化は湯量の確保、大学施設の設計では大学のパブリック性の確保など課題が浮き彫りになった。
山井
【参照資料出典元】
1.archello
Auditorium Infanta Dona
Elena de Aguilas
外観/内観/3F平面図/断面図
Headquarters Ribera del Duero Wine
外観/外観2/1F平面図



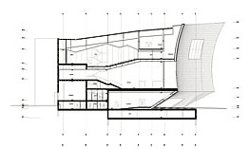
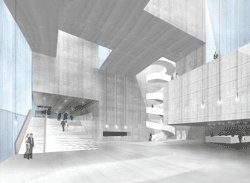
Szczecin Phiharmonic Hall
外観/内観/断面図
